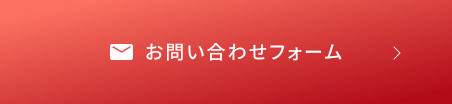新着情報Information
令和7年9月定例会で通算14回目の一般質問に!②上下水道事業
2.上下水道事業について
①課題は?
日本の上下水道事業は人口減少等に伴う料金収入の減少、施設等の老朽化に伴う更新需要の増大、専門人材の不足等の経営課題が山積しています。人口減少が著しい能代市の水道事業では令和12年度に純利益が確保できなくなる試算であり、水道料金を26.3%引き上げる方針が示されています。富根・仁鮒地区の簡易水道についても大幅な引き上げが試算され、水道事業と同一料金まで引き上げられる方針です。また二ツ井地域の簡易水道整備が令和9年度以降の着工で計画されており、約43億円の事業費が想定されています。したがって市の水道事業について今後ますます厳しい経営環境になっていくと考えます。
一方で下水道事業については、平成28年度に料金の引き上げを行い、それ以降は据え置きとなっていますが、今後は処理区域内人口が減少していく見通しであることや施設の老朽化等から将来的に経営が困難になることが予想されます。また近年の記録的な大雨や気温上昇により下水道にかかる負荷が増加していると指摘する専門家もおり、想定以上に老朽化が早い可能性もあります。よって、下水道事業も近い将来、料金の引き上げをせざるを得ないと考えます。
Answer. 本市の水道事業及び下水道事業については、収入では、人口減少等による水道料金と下水道使用料の落ち込み、支出では、老朽化した施設の更新に加え、近年の物価や労務費等の高騰による費用の増加で、厳しい経営環境にあり、その傾向はさらに強まると予想されます。このため、市民生活には欠くことができない生活インフラを担う両事業を将来にわたって持続可能なものとしていくために、健全経営に資する財源の確保が共通の課題であると考えております。
②水道事業の基本料金と従量料金の段階的引上げを行う考えは?
物価変動の影響を除いた実質賃金は多くの企業が夏の賞与を支給したものの、賃金の伸びが物価に届かず6カ月連続のマイナスとなりました。物価高騰対策として東京都は夏の4か月間、全ての一般家庭の水道の基本料金を無償にしました。このように財政的に余裕のある自治体では無償化をする一方で、人口減少や施設の老朽化等により水道料金の引き上げに踏み込む自治体が相次いでいます。そうした中で急激な引き上げによる市民生活への影響を考慮して段階的な引き上げをする自治体も少なくありません。
水道料金は基本料金と使用水量に応じた従量料金の合計金額になります。段階的な引上げとしては、基本料金を据え置き、従量料金のみ引き上げる事例も見られます。この場合、使用量が多いと負担割合が大きくなる一方で、少量世帯への負担が軽減されます。しかしながら、コスト回収の観点が最も重要であり、基本料金も従量料金も一定割合引き上げる均等改定、あるいは従量料金の低使用量部分のみ据え置きするといった複数の改定パターンを柔軟に検討すべきだと考えます。
Answer. 基本料金は、水道施設を適正に維持していくために固定的に必要とされる費用に、従量料金は、使用水量に対応して必要とされる費用に充てるものであり、生活用水の低廉な確保の原則に従い配分しております。
水道事業では令和4年度に策定した経営戦略において、給水収益の減少に伴い純利益は減少し続け、12年度には確保できなくなり、26.3パーセント増の料金改定が必要と試算しております。 市といたしましては、この料金改定は、市民生活へ大きな影響を与えると認識しており、実行に際してはこのことを最優先に捉え、段階的な引上げを含め、慎重に検討してまいりたいと考えております。
③広域化の状況は?
秋田県は国の方針に基づき、⽔道広域化推進プランを策定し、市町村の区域を超えた多様な広域連携を推進する方策を示しています。能代市は県主催の広域連携作業部会に参加し、情報収集や意見交換を行い、将来的な広域化等について検討していますが、その状況はいかがでしょうか。
一方、山形県では同様に水道広域化推進プランが策定され、鶴岡市・酒田市・庄内町で構成される「庄内広域水道事業統合準備協議会」が設立されました。当該協議会は令和8年4月からの事業統合を目指しており、広域化が着実に進んでいます。
一方で下水道事業においては秋田県が早い時期から積極的に広域化を進めてきました。令和5年には秋田県、県内25市町村、民間企業が共同で出資する株式会社ONE・AQITA(ワン・アキタ)を設立しました。民間のノウハウを活用し、下水道の持続的な管理・保全をサポートする官民出資会社であり、全国初の取組です。能代市では、下水道従事職員の減少への対応として、当該出資会社を活用した業務の効率化の検討がなされていたと思いますが、その状況はいかがでしょうか。
Answer. まず、水道事業では、令和5年3月に秋田県が策定した「秋田県水道広域化推進プラン」の中で、能代山本地域を一つの圏域としておりますが、地形の制約により施設統合等のハード連携の課題は多いと評価されております。一方、管理業務の共同発注は検討を継続することとしております。
また、下水道事業では、令和5年に生活排水処理事業等の事務を補完する目的で、県内すべての自治体と民間企業が共同で立ち上げた、株式会社ワン・アキタが設立されており、各事業体への計画策定支援、事業運営支援、技術継承支援の業務を担っております。本市では、業務に関する助言や指導、下水道事業に関する情報の提供、講習会の開催などで協力をいただいており、引き続き連携を強化してまいりたいと考えております。
このほか、令和2年から秋田県が主体となり、それまで個別対応であった汚泥処理を集約する、県北地区汚泥資源化事業を実施しており、能代終末処理場で発生する汚泥を共同処理しております。
④脱炭素化に取り組む考えは?
国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。そうした中で上下水道事業の脱炭素化も推進しており、再エネ設備や高効率設備等の導入に対する財政支援を行っています。能代市は国の方針に基づき、本年7月にカーボンニュートラル宣言を行い、「地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定しましたが上下水道事業の脱炭素化についての記述はありません。脱炭素関連の国の補助金を活用すれば財政負担の軽減を図りながら、脱炭素化と老朽化した設備の更新が可能であると考えます。
Answer. これまで水道事業では、電力使用量の抑制を図るため、導水ポンプ場等の施設でインバータ制御設備を導入しております。
下水道事業では、汚泥を消化する際に発生するメタンガスを回収 し、ボイラの燃焼に使用しており、脱炭素化の一環となっていると考えております。また、施設の老朽化に伴う設備の改築や更新の際には、国の交付金を活用しながら省エネルギー機器の導入、照明のLED 化等を実施してまいりました。今後、両事業における高効率設備や効率的な処理方法の導入に向け、有利な財源等を勘案しながら、「能代市地球温暖化対策実行計画」に基づき、脱炭素化を研究してまいりたいと考えております。
⑤人口減少が顕著な地域への小規模分散型水循環システムの導入を研究する考えは?
上下水道の課題の解決につながる「小規模分散型水循環システム」という新たな革新的技術が注目されています。使用した水をその場で再生して循環利用することで、上下水道に頼らずに水の供給と排水を住宅単位で完結させるシステムです。人口減少が著しい過疎地域等において導入することで、水供給および排水処理にかかるインフラ整備や維持に係るコストの低減が可能となります。現在、スタートアップ企業であるWOTA(ウォータ)株式会社が社会実装に向けた実証事業を行っている段階です。本年3月末まで仙北市上桧木内地区で寒冷地における実証実験が行われていましたが、当該地区に水循環システムを導入した場合、上下水道の更新費用は40年間で約10億円の削減効果があるという試算も出されています。
現在、同社は自治体向けに計画策定、ファイナンス、運用管理までの一連のプロセスを中長期的に支援するファンドを設立し、伴走する自治体を募集しています。国も5月の骨太の方針に「上下水道の分散型システムの早期実用化」を明記しており、社会実装の流れが今後加速していくものと考えます。
Answer. このシステムは生活排水を循環させて再利用するものであり、県内では仙北市で実証実験が進められております。水道、下水道ともに老朽化した配水管や管渠の更新費用の抑制、環境負荷の低減等のメリットが認められることから、こうした事例を参考にしながら、本市での導入の可能性について、研究してまいりたいと考えております。
WOTA株式会社 l Water Freedom for Everyone,Everywhere (参考資料)
※ホームページ用に簡略化して記載しています。正確な質問、答弁内容は能代市議会議事録をご覧ください。
●人口減少下では、上下水道事業などのインフラの維持が困難になっていきます。数年後には、値上げも避けられない状況が来ますので、今のうちから様々な想定をして、備えることが重要だと思います。引き続き国の動向や最新技術などを注視してまいります。