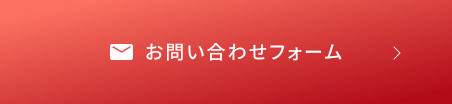新着情報Information
令和7年9月定例会で通算14回目の一般質問に!①防災(大雨災害など)
1.防災について
①内水氾濫への対策は?
能代市では8月20日夕方から21日未明にかけて記録的な大雨となりました。浸水被害が各所で発生し、避難指示は常盤、二ツ井、桧山、悪土川流域の広範囲に発令されました。
また9月2日夜から3日朝にかけても記録的な大雨となり、悪土川等が氾濫し、松長布地区では大規模な浸水被害が発生しました。避難指示は常盤、二ツ井、桧山、鶴形、悪土川流域の広範囲に発令されました。まずもって被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。また避難所が複数箇所で開設され、多くの方々が避難されていた中で、夜を徹して避難所対応にあたった職員の皆様をはじめ関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
今般の2つの大雨災害は排水処理能力を上回る記録的な大雨により内水氾濫が広範囲で発生したことが特徴であり、ソフト面、ハード面ともに内水氾濫への対策が急務であると考えます。また、どちらの大雨災害の際も激しい雨が降りしきり、各所で冠水が発生していました。そうした状況下での移動は非常に困難であったと思いますが、広範囲にわたる複数箇所の避難所を開設するにあたって支障はなかったでしょうか。
Answer. 近年、大雨の頻度が増し、集中豪雨の傾向が顕著になっております。そのため、悪土川については、「悪土川水災害対策プロジェクト」に基づき、国では米代川の流下能力向上を図る河道掘削を、県では悪土川の河川改修、河道掘削及び雑木の伐採・撤去を引き続き実施することとしております。
市では、東栄団地地域における市道の冠水頻発箇所において道路の嵩上げを実施するほか、開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置指導、住宅リフォーム支援事業による浸水対策及び住宅復旧支援等に取り組むこととしており、引き続き国・県と連携し、浸水被害の軽減に努めてまいります。
住宅への浸水被害を抑える対策としては、土のうの設置が有効であるとの考えから、特に浸水が多い地域には土のうステーションを14か所設置しているほか、道路維持センターにおいて必要とする方に対し土のうを配布しております。土のうを必要とする方が増える傾向にあることから、今後、土のうステーションの在り方について、検討してまいります。
また、今年度、下水道事業において「雨水出水浸水想定区域図」を作成することとしております。
②避難所開設の課題は?
Answer. 災害の種類や規模、発生時期、時間、地理的な要素等によって異なりますが、まずは避難者の健康管理が挙げられます。特に、感染症対策については、場合により大人数が密集して生活することになるため、感染症が発生すると一気に広がる危険性があります。そのため段ボールベッドや簡易ベッドの備蓄を進めながら、避難所における被災者の健康管理を十分に行うともに、トイレの確保等、衛生管理にも十分配慮する必要があります。
また、プライバシーの確保が課題となります。避難所ではプライベートな空間が確保しづらいことから、窃盗や犯罪の発生リスクがあるほか、ストレスによる健康被害も懸念されます。そのため市では、ワンタッチパーテーション等を備蓄し、できるだけプライベートな空間を確保できるよう努めております。 このほか、最近では、避難所での一人当たりのスペースの確保や、ペットと同伴した避難を希望される方への対応、アレルギーへの対応等、多岐にわたる課題への対応が求められております。
③職員の到着を待たずに避難所を解錠する遠隔操作システムを導入する考えは?
能登半島地震では、避難所の鍵を管理する担当者の到着が遅れ、避難してきた住民が屋外で待機せざるを得なかった、あるいは窓ガラスを割って中に入ったという事例が複数発生しました。こうした事例を受けてインターネット経由で、避難所の鍵を管理できる遠隔操作式のシステムを導入する自治体が増えています。職員の到着を待たずに避難所を開設でき、避難までの猶予時間を多く取ることが可能となります。
Answer. 市では災害対策本部において避難所開設が決まった場合、担当部局が開設準備や避難者受け入れを行いますが、災害発生の時間帯、施設までの距離や道路寸断等の交通状況によっては、職員の到着が避難者より遅くなる可能性があります。
インターネット経由で避難所の鍵を管理できる遠隔操作式のシステムにつきましては、職員が避難所に到着していない場合であっても避難者が解錠して避難所へ入れるメリットがある一方で、避難スペース以外の事務所等の管理や避難者との連絡体制等をどう構築するかなどの課題もあります。
また、避難所機能を十分に果たすためには、避難された住民自らが避難者の適切な受け入れや必要物資の把握等、自主的に避難所運営を行うことが重要となります。現在、市では各地域での自主防災組織の設立や自主防災組織等が行う避難所設営訓練等を積極的に支援しておりますので、こうした活動促進と併せて、先進事例を参考にしながら調査研究してまいりたいと考えております。
④官民連携で備蓄品のローリングストックを強化する考えは?
自治体が持つ備蓄品は賞味期限が近付くと、啓発を目的に市民に配布するか、残念ながら廃棄するというのが従来のやり方でした。最近ではローリングストックという備蓄方法を官民連携で上手く活用している自治体が増えてきました。ローリングストックとは、普段の食品や消耗品を多めに買い置きし、古い物から消費し、消費した分を買い足すという方法です。これにより常に一定量の備蓄が確保されます。
仙北市では、備蓄品をネットショップ「メルカリ」で販売し、売上金を新たな備蓄品の購入資源に充てるという官民共同のローリングストックを行っています。廃棄ロス削減と財政負担の軽減が可能となる効率的な取組であると考えます。また北海道の北後志(きたしりべし)広域5町村では、ドラッグストアと協定を結び、ローリングストックに取り組んでいます。ドラッグストアの物流拠点や店舗の商品を「みなし備蓄」として流通在庫を多めに配置し、防災備蓄とすることにより、自治体自らが保有する備蓄数を減らし、管理コストや廃棄ロスの削減につなげています。また愛知県春日井市でも、ドラッグストアと連携し、平常時は流通用の商品を防災倉庫に保管し、災害時に行政備蓄として活用しています。行政備蓄として市が購入する必要がなく、未使用時の費用負担もないため、現状では年間約100万円の経費が削減になるとのことです。能代市は防災訓練等の際に賞味期限が近い備蓄品を配布していますが、官民連携により財政負担の軽減や廃棄ロスのさらなる削減を図ることが重要だと考えます。
Answer. 市では地域防災計画において、県と市との共同備蓄品目と備蓄目標を定め、目標量を達成するため、毎年度、計画的に必要品目を購入しております。備蓄品の中には食料や飲料も含まれ、それぞれ賞味期限が定められておりますので、期限が近くなったものは、同計画で定めている市民の皆様への家庭内備蓄の指導、啓発のため、避難訓練や出前講座、防災展の際に広報活動の一環として配布しております。
ローリングストックにつきましては、庁舎で使用するトイレットペーパーについて、備蓄品を使用し、新しく購入したトイレットペーパーを備蓄品として保管しているほか、乳児用ミルクについては保育所等で使用するなど、備蓄品全般について基本的に廃棄が出ないよう努めております。 また、同計画では、流通備蓄による調達体制の整備についても定めており、事業者が通常の流通過程で保管している食料品や日用品等を、災害時に迅速かつ円滑に確保できるよう、流通業者と協定を締結しております。今後も、他自治体の状況を情報収集し、ローリングストックの強化につなげてまいりたいと考えております。
※ホームページ用に簡略化して記載しています。正確な質問、答弁内容は能代市議会議事録をご覧ください。
●今夏、能代市では度重なる記録的短時間大雨の被害を受け、広範囲で内水氾濫や冠水が発生しました。ハード面、ソフト面と対策は多岐にわたり、市単独では難しいものもありますが、なるべく早期で進むように引き続き取り組んでまいります。