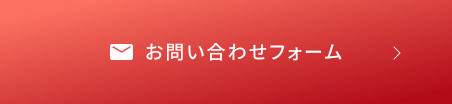新着情報Information
令和7年3月定例会で通算12回目の一般質問に!②こどもまんなか交流施設
①河畔公園に新設する方針に至った経緯は?
先の12月定例会において屋内のこどもの遊び場を河畔公園に整備する方針が示されました。
当該施設は、子育て相談や保護者の交流機能を持ち、地域の多様な世代が関わる「こどもまんなか交流施設」として位置付けられるとのことです。
また子育て支援センターの移転を伴い、行政機能が備わった施設としたいとの方針も示されました。
少子化が加速する能代市において、子どもの利益を最優先に考える「こどもまんなか」の考え方は非常に重要であり、子育て支援機能の強化は最優先課題であると考えます。
一方で今後の厳しい財政状況を鑑みると、その手法については慎重を期するべきだと考えます。本構想は廃校や学校跡地の利活用を含めた様々な手法が検討されてきたと思います。
Answer. 整備候補地の選定にあたりましては、河畔公園のほか、北高跡地等の中心市街地や東部地区、廃校舎等について、敷地面積や整備規模、交通アクセスや周辺の子育て関連施設とのつながり等、様々な観点から比較検討いたしました。
同施設は、多様な世代が遊びを通して交わり、育ち合える環境づくりを進める中核施設として整備することとしております。
河畔公園には屋外大型遊具や芝生広場、こども館等の子育て関連施設があり、施設相互の連携や一体的な活用を図ることで、こども・子育て支援の広がりが期待できることから、整備候補地としたものであります。
②より多様な機能を備えた複合施設として整備する考えは?
現在方針が示されている遊び場、交流、子育て支援機能に加えて、より多様な機能を備えた複合施設とすべきではないでしょうか。
全国の自治体に目を向けると、子育て支援以外の機能を備えたユニークな施設が様々あります。
例えば、香川県宇多津町の「南部すくすくスクエア」では放課後児童クラブとカフェを併設し、多世代の交流を促進しています。
大阪府吹田市の「まちなかリビング北千里」では、児童センター、公民館、図書館が一体となり、多世代が交流できる滞在型施設となっています。
岩手県北上市の保健・子育て支援複合施設hoKko(ほっこ)は、健診専用の設備、子どもの遊び場などの子育て世代をサポートする環境を用意しているほか、多世代が集える空間として、ホールやレンタルキッチンも備えています。
このように子育て支援機能だけでなく文化や保健といった機能が備われば、にぎわい創出や相乗効果が期待できる施設になっていくと考えます。
Answer. 基本方針において、施設の核となる機能を大型遊具等の屋内遊戯エリア、子育て支援センター等の行政機能、保護者等の交流空間とし、こどもをまんなかに保護者や地域の多様な世代が関わり合う施設として整備したいと考えており、導入する機能の詳細については、令和7年度中に策定する基本計画において検討してまいります。
③インクルーシブをコンセプトとして取り入れる考えは?
近年、障がいの有無に関係なく、誰でも遊べる「インクルーシブ公園」が増えています。
インクルーシブとは、「包括した、全てを含んだ」という意味であり、インクルーシブ公園では、全てを包み込み迎え入れるというコンセプトのもと、障がいの有無や年齢に関係なく、互いの違いを認識しながらハンディキャップのある子どもとない子どもが一緒に楽しく遊び、誰もが利用できるインクルーシブ遊具が設置されています。
こうしたインクルーシブな遊び場は首都圏を中心に全国的に増えてきていますが、秋田県ではそれほど多くありません。
インクルーシブな遊び場は異なる感覚・能力をもつ子供たちが、それぞれのペースで成長できる機会を提供できるだけでなく、保護者や祖父母といった高齢者にとっても利用しやすいといったメリットがあります。
よってインクルーシブは多様性を促進する非常に重要なコンセプトであると考えます。
Answer. 基本方針において、障がいのある方やベビーカー利用者、祖父母等の高齢者に配慮し、誰もが安心して利用できる施設として整備することとしております。
具体的な遊具の選定や設備の詳細については、基本計画の策定において検討してまいります。
【再質問】
石川県森林公園屋内木育施設「もりのひみつきち」という施設では、県産の木をふんだんに使った大型遊具が設置され、一部がインクルーシブになっています。
木材利用とインクルーシブのコンセプトを兼ね備えた先進事例であり、参考にする考えは?
Answer. 木育という観点からも検討したい。
※ホームページ用に簡略化して記載しています。正確な質問、答弁内容は能代市議会議事録をご覧ください。
●こどもまんなか交流施設が河畔公園に新設する方針が示されていますが、財政状況が今後厳しくなる中で「箱物」を建てることは慎重に判断しなければならないと考えます。
令和7年度中に策定される基本計画を注視してまいりたいと思います。